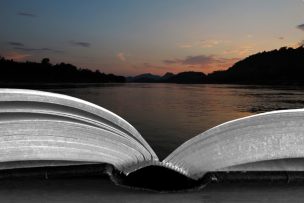管理職研修を様々な企業様で実施させて頂いており
その中で、昨今必ず入れてほしいとご要望もあるプログラムが
ビジョンの浸透です。
これはスキルとは少し異なりますが
管理職にはマストな要素、ですよね。
ビジョンの浸透が出来ていなければ
当然モチベーションも維持しにくくなります。
大きな壁にぶち当たった時に、障壁が大きくなればなるほど
それを乗り越えるためのメンタルも必要になります。
どの企業も「このビジョン共感できないわぁ」なんてものは1つもないんです。
どの企業のビジョンも、多くの人が共感できる内容です。
ビジョン=みんなで叶える大きな夢ですから、
「うちの会社だけ良ければいいよね」なんて内容は
絶対入ってないんです。
そもそもビジョンは社会的意義、ですから。
では、このビジョンを浸透させるには??ですが、一言で
個人のビジョンを組織のビジョンと融合させていくことなんです。
それはそうなんですけど、実際には…
いつも研修をしていて…個人のビジョンがない!!が一番よく出てくる悩みです。
先日の研修でも目標は分かるんですけど
夢とかビジョンとかなかなか分からなくて…
というご相談がありました。
大人になると…なかなか夢やビジョンは描けない、と言われますが、
これは原因の1つとして、考える機会が少なくなったからです。
子供はどんな大人になりたいか?をよく考える機会がありますが、
大人になると、どんな人になりたいか?を考えることもなくなってきます。
ミッションステイトメント、とも言いますが、
どんな人になりたいのか?を考えて、言語化してみることです。
例えば、自分のなりたい像をイメージして、
そのイメージを単語で表す、でも構いません。
1年に1回くらい、この考えて、言語化する時間を設けることが大事です。
これが一番身近な夢の具現化になります。
次に、これを組織=仕事に結びつける方法ですが、
仕事をしていて、嬉しいな、楽しいな、成長したな、
と感じる瞬間があると思います。
その都度、その感情やどんな時にそう感じたのか?を書き留めておきます。
この書き留めた言葉を繋ぎ合わせて「●●のために働いている=頑張っている」
といったような文を作成していきます。
これがビジョンやパーパスです。
特別なスキルは特に必要ないのですが、自分の想いや感情を言語化するのは、
やはり慣れが必要なので、都度都度、自分の感情や想いを言語化していく、
言語化しやすいように誰かに話してみる、が大切です。
まず…
①自分の夢を描く
②会社のビジョンと結びつける
③実現のための目標設定する という順番です。
是非ご自身の、部下メンバーの想いを言語化してみてください。