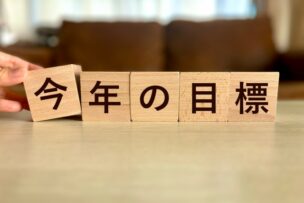週末自宅のマンションの理事会に出席していました。
小規模マンションですので10戸程度しかありません。
ですのでほとんどの所有者が出席し、意見を言って
自分たちで自分たちの財産を守っていく方針でやっています。
管理会社にお願いはしているんですが、この管理会社のフロント担当者が笑えるほどひどい。
私もこのマンションに住んで7年になりますが、担当が5人替わりました。
替わるにつれて、どんどんレベルが下がっていってます。
他にも色々課題もあり、管理組合の運営に対して、
コンサルタント会社に別途お願いをして入っていただいています。
コンサルタント会社さんに入っていただいてからは、
管理会社に対して
これはおかしい。。。
この費用の内訳は何か?
のような鋭いツッコミがこれまであり改善されていっています。
具体的には、これまで修理や修繕の際に
管理会社から提案された会社さんで修理修繕をしていましたが
これがすごく高くて…。
それをコンサルタント会社さん経由で相見積もりを取り
妥当だと思うところで修理修繕を変更したりで全体的なコストカットが出来ています。
先日の理事会で、月次決算報告を管理会社さんがされたのですが…。
コンサルタント会社さんが
「これは何の嫌がらせでしょうか??」とから始まり、
「我々に対して半年間支払いがされていません。
これまでにも何度も2ヶ月3ヶ月遅れるというのあったんですが、
半年間支払われていないと言うのはあまりにもひどすぎませんか?
これまで何度も請求書を送って支払ってくれと督促はしてるけれども、
一向に支払われる気配がない。
これに対してどう考えているのか?」とありました。
そこで我々も改めて月次決算書を細かく見てみると
確かに半年間支払われていない。ずっとゼロなんです。
一方、管理会社経由のものについてはきちっと毎月支払われている。
フロント担当者は…しれっと
「ああ、忘れてましたね。」とか「そうでしたか?」みたいな感じで
のらりくらりと返答され、「社に帰ってから確認します」と。
他の件(以前から依頼している)はどうなってますか?
の質問にも
「そうでしたか?まだですね。確認します。」
終始この繰り返しです。
このフロント担当者に替わってから、あまりにもひどくなり、
全然仕事をしてくれていない、という感覚が住民間でも大きくなり
管理会社自体を変更する方向で進んでいます。
これまでに何度もフロント担当者の上司や会社に対して
改善のお願いをしてきましたが、改善されるどころかひどくなる一方です。
かなりの大手企業さんですが、この数年で信頼度超マイナスです。
(それまでそんなに悪いイメージを持ってませんでしたが…
グループ会社も含めて今はお付き合いしたくない会社になりました。)
改善には時間も掛かるし…
担当を変更するにも次の担当者の問題もあるし…
とある程度管理会社の事情も理解してきたのですが、ここまでくると
「この管理会社は、うちのマンションの契約を切りたいんだな」
と思わざるを得ません。
(コンサルタント会社さんからもおそらくそうだろう、と言われました)
うちのマンションは小規模なので、管理会社にしてみると割に合わないんです。
やらなくてはいけない仕事は大規模マンションと一緒なので、
利益が取りにくい(大きな利益が出ない)。
またマンションも古く古参の方々もいるし、いわゆる「モノを言う住民」です。
言い換えれば…
管理会社としてはやりにくい。めんどくさい。いろんなことを言われて大変だ。
ですので、会社として「このマンションは割に合わない」と判断をされたのだと思います。
理屈としては分かりますが…
このような扱いをされると気持ちの良いものでは当然ありません。
管理会社を変更するとしても、こういう終わり方って良くないよなぁと
単純に思うんです。
契約更新するかしないか、に関係なく(例え契約が終了するとしても)
会社のブランド力、イメージって大事で…。
でも会社は無形物です。
そのイメージは、マーケティングなども当然左右しますが
ダイレクトにフロント担当者の人間性です。
それを今回の件で実体験をもって経験しました。
弊社は小さな小さな会社ですので、ほぼすべてのお客様のお顔が
(担当者だけではなく、私も)見えています。
単純な紙の上の数字ではなく、お客様のお顔が見えるからこそ
一旦の利益はどうあれ、お役に立ちたいと純粋に思います。
それがある意味我々の強みだと、今回の件で改めて気づきました。
最後に、一番の笑い話(腑に落ちたところ)。
このフロント担当者、本当にある意味メンタルがめちゃくちゃ強いです。
これだけ毎回毎回言われても、傷ついたり落ち込んでる様子が1ミリもない。
(だから改善もないんですが…)
私は知らないですね。
私は聞いてないですね。
私は分からないですね。
常に我関せず、なんです。
無関心のメンタルは最強とよく言いますが…
笑えるくらい最強でした。
(お客様ですから無関心は絶対ダメですけどね。。。)