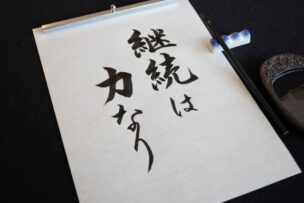先週は少し暖かく、秋らしい気温でしたが
今週は一転して、寒い冬模様になりましたね。
娘の学校もそうですが、インフルエンザが流行っているようです。
皆様も是非お気をつけくださいませ。
さて、先週も今週も研修三昧の山口ですが
先日行った研修でこんな質問が出ました。
昔と違って、サービス残業や必要のない残業を強いることは
もちろん当たり前にダメですし、そんなことは誰もしていません。
ただ…始業時間ギリギリ、ほんとに1~2分前にしか来ない社員がいます。
こうゆう社員に、もう少し早く来るように(せめて5分前)促したら…
●時から開始ということは、その時間ピッタリに来ていいですよね?
5分前に来い、というなら、その5分間の給与は支払ってくれる(残業代)ってことですよね?
支払いなしということであれば、労基法違反ですよね?
と返されました…。
これってそうなんですか??と。
この質問、よく管理職研修等でも頂きますし、
ハラスメント研修でももらいます。
そして年が明け、新入社員研修を企画する段階になると
商談でもよく頂く質問です。
新入社員研修では必ずお伝えしていますが…
労基上ではそうです。
●分前に来なさい、と指示命令することは出来ません。
ただ、働く心得(=社会人としての心得)があります。
その中に、時間の余裕を持ち、業務に取り組もう、という心得があります。
心に余裕が出来ることで、その後の集中が高まりますし
余裕を持つことで、相手に対する心配りにも時間を割け
そして何よりも自分の心に余裕を持つことで
前向きに取り組むことが出来ます。
(茶道の心得でビジネスの心得にも通じるもの)
仕事とはそもそも相手の期待以上に応えることで成り立ちます。
この人に仕事を任せてみよう、と思うのは
大前提その人を、人として信頼出来るからです。
では、この信頼、どうやって築くのでしょうか?
信頼とは、持って生まれたものではなく、性格でもなく
その人の普段の言動から生まれるものです。
いつも時間ギリギリ、という人に大事な仕事を任せてみよう、
になるでしょうか?
これ、時間だけのことだけではありません。
教えてもらったことを復習しない。
やるべきことを後回しにする(もしくはやらない)。
仕事の選り好みをする。
気分の浮き沈みが大きい。
愚痴や文句が多い。
挨拶をしない。
話しの仕方(特に聴き方)が雑。
仕事の仕方がいい加減(適当)。
などなど。
これらは能力スキルではありません。
何かの専門知識が必要なわけでも、ものすごく経験が必要なわけでもありません。
単純に心得、なんです。
でもこの心得が出来ていないと
人はこの人って信頼できないな、と感じるんです。
さて、前述の質問への返答です。
●時間働く、という時間単位で働くのは、アルバイトの心得です。
正社員であれば、期待されている業務に対しての対価です。
正社員だからこそ、これらのビジネスパーソンとしての心得は
持っておいてほしいものです。
特に始業時間については、1日の始まり。
今日のスケジュールややるべきことを整理する時間も必要です。
だから10分くらい前には来て、準備をしましょう、です。
もちろんこれは心得ですから、無理に強いることは出来ません。
でも新人にはいつも伝えますが、
自分のしていることは全て、何らかの形で自分に返ってくるんです。
自分がした努力も、自分が手を抜いたことも、全て自分に返ってきます。
私もいろんな方と商談(私がお客様の立場)します。
時間にルーズな人、準備不足な人、礼節を守らない人とは
どれだけ商品サービスが良くても仕事は依頼しません。
そもそもそんな人と一緒に仕事をしたくないからです。
あっという間に今年も終わりが見えてきましたね。
残り1か月少しになりました。
改めて自分の普段の言動を見直すきっかけにしたいと思います。