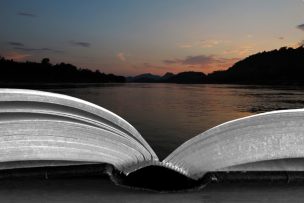長いGW明け、という会社様も多いのではないでしょうか?
GWが過ぎれば夏、と言ってもいいほど暑くなりましたね。
皆様はリフレッシュできたGWでしたか?
私はこのGW、さっそく今年初の潜りに石垣島へ!
青い海と深い海に癒されて帰ってきました。
潜れば潜るほど、海の魅力に引き込まれ、とうとうダイビング用のカメラも帰りの飛行機待ちの間にポチってしまった山口です。
さて、GW前のメルマガでお話していた弊社の営業研修。
百貨店で4時間並んだ人と、相手に圧倒的差を付けて利益を出した人。
総合評価は4時間並んだ方が圧倒的に高かったんです。
さて、その理由は大きく2つあって…
1つは前回のメルマガでお話した「相手に合わせた商品か否か?」になります。
そしてもう1つは…
1つ目の理由以上に大きな差をつけた理由。
どこまで新しい分野で、よりチャレンジをして挑んだのか?なんです。
百貨店で4時間並ぶことについては、
もともとの彼のパーソナリティーから考えても得意分野ではありません。
むしろ一番苦手といってもいいかもしれません。
自分のよく知っている領域(興味のある領域)でもないんです。
ただ自分の知らない領域でチャレンジをしてみる。
そして4時間1人で並び切るという、ある意味「1番しんどい方法」を選んでるんですね。
一方利益額が大きく出したけど、最も自分の得意とする領域で
よく知っている領域でそこから出ようとせず、
そしてこの相手よりも利益を大きく出すという目標に目をとらわれてしまって、
新しいことにチャレンジをする=汗を流して努力をする方向性が少しずれてしまった。
彼の方が評価は実は低いんです。
彼らに伝えたのは…
2人ともとっても頑張ってる事はよく分かっているし伝わっています。
決して手抜きをした、とかなまけた、なんてことは2人ともありません。
2人とも、とっても「努力」をしたんです。
ただこの「努力」の方向性について…。
努力は報われる、私は間違いだと思います。
正しい努力は報われますが、間違った方向性の努力は報われないんです。
人生いろんな岐路に立った時、いくつも選択肢があります。
その中でついつい人間は、1番楽な方法を選びがちです。
防衛本能の1つと言っても良いかもしれません。
でも常に1番楽な方法を選んでいったら、どうなるでしょうか??
新しい知識も経験も増えないし、
居心地が良くて安全領域の中にいるので、そこからなかなか抜け出したくありません。
恐ろしいことに、これは無意識で選択してしまいます。
意識的に「楽な方を選ぼう」とは多くの人は最初は思わないんです。
無意識だからこそ、怖い「陥りやすい穴」だと私は思います。
では一方で、1番しんどいだろうなぁという道を選んだら、どうでしょうか??
当然自分の知らないフィールド、自分の知らない世界、
そしてそこで勝負するには知識が必要になります。
そしてそれを耐え抜く根性もいるでしょう。
でもこれを続けていくと、どうでしょうか??
実はこれが大きな差になります。
研修でよく、「20代で必ず身に付けておきたいこと」の考え方をお伝えしますが、20代でついた差は一生埋まりません。
なぜなら20代でつけるべき事は、知識やスキル以上に大事なことで、これは考え方や取り込み方なんです。
20代で1番楽な方法を選んでしまったら、
その後30代40代となると当たり前ですが、もっと楽な方法を探すようになります。
これ営業で言うと典型なんです。
既存顧客にばかり営業してしまう。
新規顧客の営業が苦手だ。
なぜか??
既存顧客の方が絶対楽なんです。
信頼関係は築けているし、その企業様においても実績がある。
だから提案も通りやすいし、ヒアリングもしやすいんです。
一方新規営業では、とにかくまずアポを取るところからがしんどい。。。
アポを取っても相手の人となりもわからないので、
ヒアリングも難易度が高くなる。
そこから信頼関係を積み重ねるには時間もかかる。
当然新規営業になると、よほどのことがない限り、競合他社とのコンペになります。
競合に勝ち抜くだけの提案が必要になってきます。
でもこれを続けていくと、どうでしょうか??
新規営業ができるスキルがあるんだったら
当然既存顧客の拡販もできるんです。
これが大きな差になるんです。
彼らにも少しでも伝わってくれたらいいなぁと思います。
これを1つの良い経験として、
常に自分の前に現れるたくさんの選択肢の中で、
「1番しんどい道を選ぶ」
そんなふうに進んでいってくれたら…と期待してなりません。
一緒に頑張ろう!若者たち!!!!