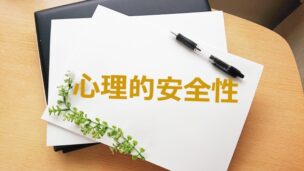先日ある会社様で、若手向け研修を実施をしてきました。
最近このメルマガでもよく書きますが、
最近の人たちは本当にGoogle信者だなぁと思う場面がたくさんあります。
ありがたいことに私は自分の会社だけではなく、
いろんな会社の若い方々、特に20代前半の方々と接する機会もたくさんあるので、
なるほどな…そういうふうに取るんだなぁ…とか、
なるほどな…そういうふうに全部信じるんだなぁ…
ってことを目の当たりにするので、そんなもんだなと理解が進みます。
これを自社のメンバーだけで接していると
なんでそんなふうに取るんだよ…とか
なんでそんなふうに考えるんだよ…と
自分を基準にしてしまって、なかなか受け入れられなかったり
理解ができないことがあるのではないかなと
一方では思ったりします。
先日、具体的にこんなことがありました。
休憩時間の間にいろんな方とお話をしてたんですが、
こんな質問をもらったんです。
先生、もっと楽に稼げる職業って他に何がありますか??
先生、もっと楽に働きたいんですけど、どうしたらいいですか??
という質問をいただきました。
まぁこれって…
そんなことを普通聞くか??が正直な第一声の心の声です。(笑)
研修の講師に対して、自社の仕事の仕方や、
自分のスキル向上・キャリア形成等の質問ではなく、
他にどんな職業がもっと楽にありますか?
いろんな会社行ってるんですよね。どの職種が1番楽そうですか??
って質問はなかなかしにくいんじゃないの?
とファーストインプレッションでは思うんですが、
そこは研修講師ですから、言わずに…
その後よくよく話を聞いていると…
彼らはこんな風に言うんです。
「Googleで調べたら、実は営業は、親が子供に就かせたくない職業トップファイブ
に入ってるんですよ。」や
「営業の仕事ってノルマがあるじゃないですか。
だから鬱になる人って多いんですよ。(googleでは)」と。
いわゆるGoogle情報を彼らは引き合いに出してきます。
でもそれってもちろんその情報も正しいかもしれないんだけど、
そうじゃない人もいっぱいいるよ。
だって私は30年近く営業の仕事をやってますが、
いつも楽しいと思うし、営業ほど楽な仕事はないと私は思うし、
それってあくまでもGoogleの検索の結果であって、
人によってもちろん向き不向きもあるだろうし、合ってる合っていないもあるし、
職種だけじゃなくて、会社の雰囲気や会社の風土みたいなものもあるし、
だから一概に、googleの結果が全て正しいとは言えないよ。
と話すと、そっかと彼らは結構納得するんです。
インターネット世代の怖さとも言いますが、疑問に思ったらすぐに検索する。
そしてその検索結果で出てきたものを、あたかも全員の意見だったり、
あたかもそれが真実のように捉えてしまっているんです。
インターネットやスマホがなかったときには、
いろんな人に話を聞いて、いろんな人の意見を聞いて、
その中で自分で解釈をしたり、自分でもう一度考えることが
癖付いていたように思うんですが、
便利なことにGoogleがあるので、検索をしてその答えが全て正しいと思い込んでしまう。
これはどの若者にもある傾向だと思います。
ですので受け手側も
なんでそんな質問するんだよ!?
なんでそんなこと聞くんだよ!?
それってどういう意味で言ってるんだよ!?
と思ってしまうことはよく分かります。(私も思いますし。)
ただ一方で、一度深呼吸をして考えてみてください。
Google検索したらこう出てくるんだなぁ、がわかると
だよね、と思える。
更にもう1歩踏み込んで対話をしてみる。
するとなるほどなぁ。だからそういう思考性なんだを理解するようになると思います。
ぜひ1歩踏み込んだ対話を意識してみましょう。
最近特に、このなんとも言えない矛盾なようなものに悶々とします。
本来は便利で効率的なものだったし、
本を片っ端から読み漁るよりも、はるかに早く広く様々な情報を得て
以前よりも博識になり、以前よりも思慮深くなるはずが…
簡単に出来過ぎてしまうが故の、思慮の狭さを生み出してしまう。
なんとも言えない矛盾ですね。
だからこそ、インターネットに使われるのではなく
使う側の人間でいることを忘れてはいけないと思う今日この頃です。