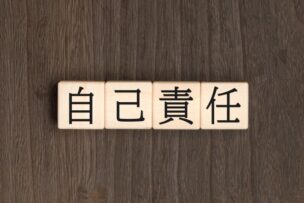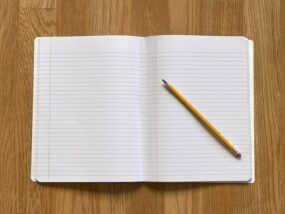先週ある会社様で、若手向けのキャリア形成研修を実施いたしました。
若手向けといっても、今回の実施グループは1人を除いて、
今年の4月に入社した新入社員の方々です。
その方々に対して働く考え方心得、これまでの棚卸し、
そしてチームワークを育む内容を実施してきました。
新入社員のある方がですね。
感動する位本当に素晴らしい方がいらっしゃったのでご紹介をしたいと思います。
彼は研修開始30分ぐらい前に会場にもう着いていたんですが、
とにかく挨拶が本当にすごい!!!
私だけではなく、みんなに一人一人のところに行って
「おはようございます。●●さん久しぶりだよね。」
「おはようございます。今日は1日同じチームで頑張ろうね。」
「おはようございます。●●さんはどこに配属になったの??」
と来る人来る人みんなに、自分から積極的に声をかけていて、
しかももう、こぼれるばかりの笑顔で積極的にコミニケーションを取りに行ってるんですね。
そして研修が始まってからも、常に本当にきれいな姿勢で座っています。
そして話を聞く時も、体ごと、こちらを向いて聞いているんです。
私も会場の中をいろいろ動きながら話をしたり、全員と目が合うようにいろんな人の顔見ながら話をするんですが、
とにかく私が動く方向に体を向けている。
私がいろんなところに目線が行くと、私の顔をずっと追っているのが目の端でわかるんです。
そして私と目が合うと…うなずきながら、顔の表情を変えながら聞いているんです。
とにかくこの反応感がすごい!!!
なかなかここまですごい人ってほとんどいないんです。
私はもう本当に感動しまくりで、彼はすごいなぁと思っていました。
そして、働く考え方心得のプログラムのところで
当たり前のレベルを上げようねと言う話をしたんです。
やっぱり当たり前のレベルがすごい人っていうのは周りに対する影響力がすごい。
その人の言動が周りに対して良い影響を与えるよね。
だからほんの小さな事でも、その小さなことの当たり前のレベルを上げることが
結果、その人の人格を作ります。
でも当人は当たり前にしているので、している感覚があまりない。
それが10年も経つと追いつけないくらい差がついているんだと。
という話をしました。
そしてグループワークで…
例えば予習復習の仕方、報連相の仕方、気遣いの仕方、挨拶の仕方など
この人すごいよねって言われる人ってどんなことをやってるだろうか?
具体的に言動を考えてみましょうというディスカッションワークをしたんです。
彼のグループでは挨拶のところで…
「これ!俺答えわかるから言わせて!!」と発言をしたんです。
「挨拶っていうのは相手を変えることなんだよ!」と、キラキラした目で話してるんです。
周りの人が、「具体的な言動だから、相手の心を変えるってどういうことなの?」と聞くと、
「例えばね、相手の人が『今日はなんかしんどいなぁ』と思っている雰囲気だとするよね。
すると僕が、『おはようございます!!!』ってすっごい元気に挨拶しますよね。テンション上がりません??」
と話すとみんなつられてニコニコしながら「上がる!上がる!!」となっていたんです。
(もちろん彼のグループに発表してもらいました。)
そう。彼の挨拶(挨拶だけではなく話し方そのもの)ってテンションが上がるんです。
「支社の中で1番若いけど、そしてたいしたこと(仕事)もしてないけど、
挨拶だけは絶対誰にも負けない気持ちで毎日やってるんです!!」
と本当にキラキラした目で話してたんです。
これね、ほんとすごいことだと思うんです。
挨拶って毎日のことですが、これだけ挨拶に全力投球できる人ってそんなにいないです。
相手を元気にしよう。
この空間を一緒に作ろう。
今日も一緒に頑張ろうね。
そんな想いを込めて挨拶をする。
素晴らしいなぁ。本当に感動しました。
そして彼は、挨拶だけではなく、とにかくすべてに全力投球でした。
ディスカッションもワークも、とにかく彼は全身から「全力でやってます」オーラが出るんです。
グループの他のメンバーからも「●●くんって絶対可愛がられるよね」って言われていました。
私もそうだと思います。
私が上司でも彼のことを全力で応援したくなります。
だって全てに一生懸命ですから。
研修中も彼に引き上げられて、いろんな人が共にどんどんどんどんキラキラしていって
一生懸命になっているのが空気感でわかりました。
彼はまだ入社して9ヶ月です。
しかしもうすでに、周りを良くする空気感を作るリーダーシップを存分に発揮していたんですね。
私も今回の研修で彼と一緒に参加をさせていただいて、本当に楽しい、素晴らしい時間を過ごさせて頂きました。
素晴らしい1日をありがとうございました。