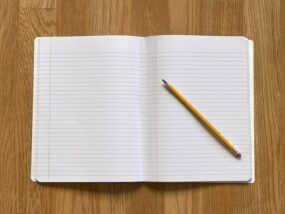先週ある会社様でリーダー養成研修を実施していたのですが…
そこでのプログラムの1つに
「どんどん時代が進化している中で
今当たり前になっていることが、将来当たり前にならないことが
多々ありますよね。
様々な問題や様々な進化がある世の中で、
具体的に将来自社や自分の仕事にどんな影響を与えるのか?
を論理的に具体的に考えよう」
というものを行いました。
たとえば、私が新卒の時の約25年前と今とでは当たり前が違います。
①人口の多い団塊Jrで、超買い手市場でしたので、
辞めたら次の転職先なんて見つからないよーが当たり前でした。
なので、多少しんどくても、嫌なことがあっても、頑張る!が普通でした。
今は少子化で超売り手市場ですよね。
②ハラスメントもまだまだ一般的ではなかったし
多様性とかも認められない世の中でしたので…
こうあるべき、が主にあって、そんなものか、と思っていました。
これ、否定的ではなくそういうものなんだ、という感じです。
③私が新卒の時には、オンラインなんてものはなかったし
PCも営業はまだまだ主流ではなくて
とにかく足繁く通う、が主でした。
メールアドレスとかもまだまだ個人のものは持ってなくて
係で1つ、くらいの感覚で、FAXと電話、そして対面でした
④PCでの入力業務はほとんどなくて、
手書きでいかに早く見やすく書くか?が主だったので
字がきれいな人、ってやっぱスキルあるよねーと言われました
という風に違ってますよね。
当然この先もどんどん変わっていくんです。
ですからネット上で、今後なくなる職業ランキングとかありますね。
受講者の多くが30代前半くらいの方々でしたが…
発表してもらうと、自分の職種はきっと30年後にはこんな世の中になっているから
なくなっている可能性が高い、や
自分の職種はなくなりはしないけど、今のこのスキルはきっと必要なくなって
こんなスキルが必要になるんじゃないか?
といった意見が挙がってきました。
大事なことは、将来のことなので誰にも分かりません。
でもこうなるんかもしれない…と前向きな危機感を持つこと。
そこから、今出来得ることは「何があっても学び姿勢を貫くこと」しかない
に気付くことです。
ダメなのは…
私の仕事なくなっちゃう!!と変におびえたり
悲壮感を持って動けなくなること。
危機感を持つことは大事ですが、悲壮感になって動けなくなるのは本末転倒です。
危機感を持ちながら、だからどうしたら??を考えていくこと。
将来のことなので、不確かなことはみんな同じです。
でもいつの世も、どうなるんだろう?どうしたらいいんだろう?を
広い知見から、斬新なアイデアを出して、すごい推進力で進めてた人が
結果、次の時代が来ても生き残れます。
だから、日々学ぶことって本当に大事だと思います。
もう1点。
学ぶことって、「慣れ」だし「習慣」なんです。
学んでいない人が、必要になった時に学ぼう!にならないんです。
だって学んでなかったら、必要な時すら気付かないからです。
だから気付かないまま、今までと同じようにしていたら
目に見えて変化し終わった後にしか気付きません。
そこから学んでも遅いんです。
そして学ぼうと思っても、慣れてないのでしんどい…。
だから途中で諦めちゃう…
この繰り返しです。
改めて、自分で学び気付くことって、本当に原点だと感じた次第です。