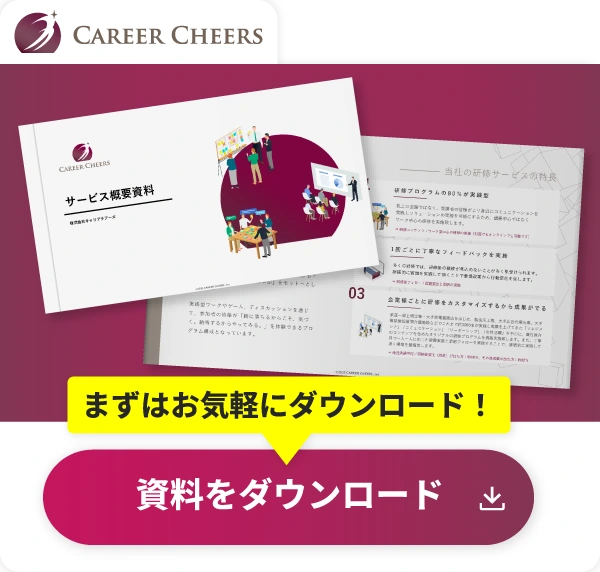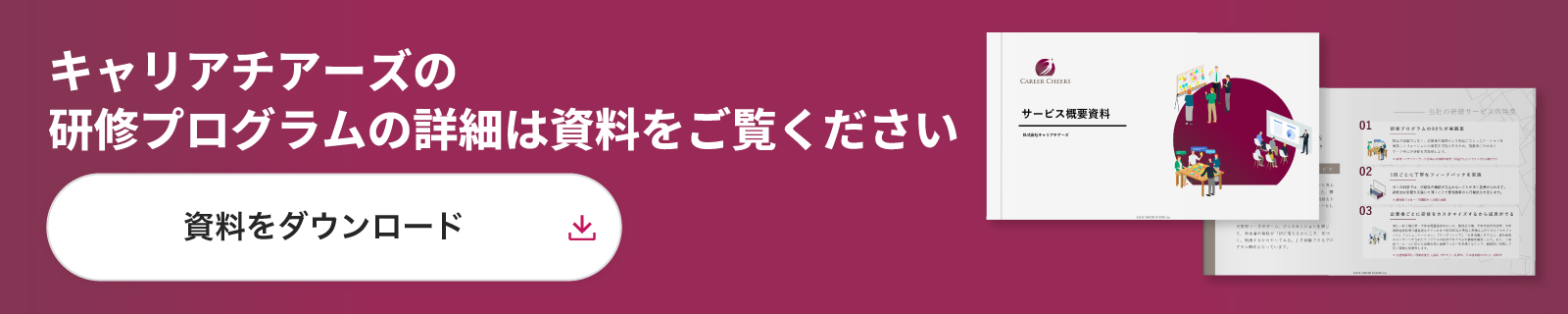
DESC法とは?自分の意見を伝える流れを具体例でわかりやすく解説
仕事で上司や部下に意見を伝えるとき、会議で意見がぶつかるとき、あるいは交渉や面接の場など、「どうすれば相手を不快にさせずに本音を伝えられるのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。感情的に言い合えば関係が悪化し、遠慮しすぎれば自分の意見が伝わらないというジレンマを解消するのがDESC法です。
DESC法は「事実を伝える」「気持ちを表す」「提案する」「選択肢を示す」という4つの流れで会話を組み立てる手法です。この記事では、その基本の考え方から具体的な使い方、メリットや注意点、他の手法との違いまでをわかりやすく解説します。
最後まで読むことで、ビジネスにも日常にも役立つ実践的なコミュニケーションの型を身につけられるでしょう。
DESC法とは?
DESC法(デスク法)は、相手を尊重しつつ自分の意見をしっかり伝えるためのコミュニケーション手法です。名前は「Describe(状況を伝える)」「Express(気持ちを表す)」「Suggest(提案する)」「Choose(選択する)」の頭文字に由来しています。
1970年代にアメリカの心理学者によって提唱されたこの方法は、会話を4つの流れに分けることで、感情的な衝突を避けながら論理的で建設的な話し合いを可能にします。ビジネスの現場ではもちろん、日常生活でも活用できるアサーティブ(攻撃的でも受け身でもない自己主張)のスキルとして注目されています。
「相手を不快にさせずに本音を伝えるにはどうしたらいいのか?」という悩みは、多くの人が抱える課題です。DESC法はその解決策として、多様なコミュニケーションの場で活用できる実践的なフレームワークなのです。
DESC法の4つの流れ
DESC法は「状況を描写する」「気持ちを表す」「提案する」「選択する」という4つの流れに沿って会話を進めます。この順番で話を組み立てることで、相手を追い込むことなく自分の考えを伝えられ、納得感のある対話がしやすくなります。以下では、それぞれの流れを具体的に見ていきましょう。
Describe(状況を客観的に伝える)
最初のステップは、事実をそのまま伝えることです。ここでは感情や評価を交えず、確認できる事実だけをシンプルに伝えます。例えば「今週の会議資料がまだ提出されていない」というように、客観的に確認できる状況を示すイメージです。
事実から会話を始めると、相手が「責められている」と感じにくく、冷静に話を聞く土台が整います。逆に最初から感情的に伝えると相手が身構えてしまい、建設的な話し合いにつながりません。ポイントは「誰が聞いても同じように理解できる事実」を選ぶことです。
Express(自分の気持ちを率直に表現する)
次に、自分がどう感じているかを率直に伝えます。このとき重要なのは「私は〜と感じている」と自分を主語にして話すことです。例えば「資料が遅れると、私は全体の進行が遅れるのではと心配になります」と伝えれば、批判ではなくあくまで自分の不安や困りごとを共有する形になります。
感情を抑え込みすぎても相手に伝わりませんが、怒りや不満をそのままぶつけると関係が悪化します。落ち着いたトーンで「なぜ困っているのか」「どんな影響があるのか」を説明することで、相手も理解しやすくなります。
Suggest(相手に提案を伝える)
3つ目は、解決に向けた提案を行うステップです。ここでは自分の要望を一方的に押し付けるのではなく、「こうしていただけると助かります」といった形で実現可能な代替案を示します。例えば「次回から提出期限を前日に設定すれば、全体の準備がスムーズになると思います」と具体策を提案します。
大切なのは、相手に選択の余地を残しつつ、問題解決につながる方法を一緒に考える姿勢を示すことです。提案を柔らかく伝えることで、相手も受け入れやすくなります。
Choose(最終的な選択肢を示す)
最後に、相手の答えに応じて次にどう進めるかを一緒に決めます。提案が受け入れられれば「この方法で進めましょう」と合意できますし、難しい場合は別の選択肢を示すこともできます。例えば「もし難しければ、私が事前にドラフトを確認する形でも対応できます」といった代案です。
あらかじめ複数の選択肢を準備しておくと、話し合いが行き詰まるのを防げます。最終的に「お互いにとって最も現実的で納得できる方法」を選べるのが、このステップの大きな強みです。
DESC法を使うメリット
DESC法を取り入れることで、コミュニケーションはよりスムーズで前向きなものになります。ここでは代表的なメリットを三つ取り上げて紹介します。
信頼関係を築きやすくなる
DESC法は、相手への配慮と自分の率直な表現を両立できるため、信頼関係の構築に役立ちます。最初に事実を整理し、その上で自分の気持ちや提案を丁寧に伝える流れは「誠実に向き合ってくれている」という印象を相手に与えます。
例えば上司に改善を求める場面でも、ただ批判するのではなく「この状況が続くと業務に支障が出そうで心配です」と伝えれば、相手も真剣に耳を傾けやすくなります。信頼は一朝一夕で築けるものではありませんが、DESC法を繰り返し実践することで「この人はきちんと対話できる」と認識され、ビジネスでもプライベートでも人間関係の土台を固めることにつながります。
建設的な議論ができる
DESC法のもう一つの大きなメリットは、感情的なぶつかり合いを避け、建設的な議論に導けることです。流れに沿って事実から始めることで「感情よりも現状を整理する」モードに入ることができ、議論が前向きになります。
例えば会議で意見が割れた場合も、まず両者の事実認識を確認し、その上で「私はこの点が心配です」と気持ちを共有すれば、争点が明確になります。さらに代替案を提案することで「どちらの意見を押し通すか」ではなく「どうすれば全体にとって良い解決になるか」に焦点を移せます。このようにDESC法は、問題解決に直結する議論を促し、意思決定のスピードや質を高める効果があります。
誤解や衝突を減らせる
人間関係のトラブルは、多くが「伝えたつもり」「分かってもらえなかった」という誤解から生じます。DESC法では事実と感情を分けて伝えるため、意図が誤って解釈される可能性が低くなります。また「私はこう感じています」と自分を主語にして伝えることで、相手を攻撃する印象を与えにくく、反発を招きにくいのも特徴です。
さらに、提案と選択肢を提示することで「押し付けられた」と感じさせず、相手の主体性を尊重できます。こうした姿勢が積み重なることで、不要な衝突や摩擦が減り、結果として仕事の進行も人間関係もスムーズに進みやすくなります。DESC法は、ストレスを減らしながら本音を伝え合える健全なコミュニケーションを実現する有効な手段なのです。
DESC法の具体例
DESC法は、実際の会話に落とし込むことで効果を実感できます。ここでは職場やビジネスシーンを中心に、よくある場面を取り上げて簡単なセリフ例で解説します。自分の状況に置き換えながら読んでみてください。
職場で上司や部下と意見を交わす場面
上司から無理な依頼を受けたとき、ただ「できません」と言うと角が立ちます。DESC法を使えば、冷静に状況を説明し、代替案を提示できます。
- Describe:「現在、別のプロジェクトの締切が明日で、対応に追われています」
- Express:「このまま新しいタスクを受けると、どちらも中途半端になってしまいそうで不安です」
- Suggest:「もし可能でしたら、締切を来週に延ばしていただくか、他のメンバーと分担させていただけないでしょうか」
- Choose:「どちらの方法が現実的か、ご判断をお願いできますか」
この流れなら、単なる拒否ではなく「どうすれば解決できるか」を一緒に考えている印象を与えられます。
会議で意見が分かれたときの使い方
会議では意見が対立すると感情的になりやすいものです。DESC法を使うと、冷静に論点を整理し建設的な提案ができます。
- Describe:「A案はコストが高いが効果が見込めます。B案は低コストですが効果は不確実です」
- Express:「私は、確実に成果を得たいのでA案の方が良いと感じています」
- Suggest:「一度テストをしてデータを比較し、最終判断するのはどうでしょうか」
- Choose:「合意いただけるならテスト計画を立てます。難しい場合は別の方法も検討します」
こうすることで、対立を「勝ち負けの争い」ではなく「問題解決の協力」に変えられます。
クライアントとの交渉に活かす方法
取引先から値下げを求められたときも、DESC法を使えば関係を損ねずに対応できます。
- Describe:「原価や品質維持のため、大幅な値下げは難しい状況です」
- Express:「御社とは長くお付き合いしたいので、品質を守ることを優先したいと考えています」
- Suggest:「値下げの代わりに、今回はオプションを無料で追加させていただければと思います」
- Choose:「ご提案を受け入れていただければ、価格は据え置きでもより効果的にご利用いただけます」
このような交渉の場でも、単なる拒否ではなく誠意を示しながら代替案を提示することができるでしょう。
面接や自己アピールで活用する方法
就職活動の自己PRでも、DESC法を意識すると論理的かつ具体的に自分を伝えられます。
- Describe:「大学のテニスサークルで部長を務め、20人のチームをまとめ年間計画を立てました」
- Express:「その経験から、メンバーの意見を引き出しチーム全体を成長させる大切さを学びました」
- Suggest:「入社後はこの経験を活かし、チームで協力しながら成果を出していきたいと考えています」
- Choose:「もし詳しいエピソードにご興味があれば追加でご説明いたします」
事実と気持ちを整理して話せるため、面接官にも伝わりやすく、説得力のある自己PRになります。
DESC法のデメリットと注意点
DESC法は多くのメリットを持つ一方で、使えば必ずうまくいく魔法の方法ではありません。実際に活用する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。ここでは代表的なものを紹介します。
相手が必ず納得するとは限らない
DESC法は自分の考えを筋道立てて伝えるための有効な方法ですが、必ず相手を納得させられるわけではありません。相手にも譲れない事情や価値観があるため、どんなに理論的に説明しても受け入れられないケースがあります。
特に利害が対立している場合や、相手が強硬な態度を崩さない場合は合意に至らないこともあります。大切なのは「DESC法は相手を説き伏せる技術ではなく、お互いに納得できる点を探す方法」と理解しておくことです。思い通りにいかなくても「話し合いを通して理解が深まった」と捉え、必要に応じて別の解決策を検討する柔軟さが求められます。
感情的にならない工夫が必要
DESC法は冷静さを前提とした手法です。話し合いの途中で感情的になってしまうと、本来の効果は薄れてしまいます。例えば、語気が強まったり皮肉を交えたりすると、相手は防御的になり対話が難しくなります。
これを防ぐには、事前に伝えたい内容を整理しておくことが有効です。箇条書きにして準備すれば、感情に流されず落ち着いて話せます。また「私はこう感じています」と自分を主語にすることで、相手を責めている印象を避けられます。
感情が高ぶりそうになったときは、一呼吸おいてから話す、自分の困りごとに焦点を当てるといった工夫を取り入れましょう。終始冷静な態度を保つことが、DESC法を効果的にするポイントです。
選択肢を複数用意する重要性
DESC法の最後の流れ「Choose(選択する)」では、相手に提案を受け入れてもらうかどうかを決めてもらいます。しかし一つの案しか用意していないと、相手がNOと答えた時点で話し合いが止まってしまいます。
そこで重要なのが、あらかじめ複数の代替案を準備しておくことです。例えば「納期を延ばす」が難しい場合は「別のメンバーと分担する」といった具合に、いくつかの選択肢を持っておけば柔軟に対応できます。
準備には時間や労力がかかるため手軽とは言えませんが、それでも交渉の行き詰まりを防ぎ、双方が納得できる着地点を見つけやすくなります。DESC法を活用する際には「代案を持っておくこと」が欠かせない準備だと心得ておきましょう。
他のコミュニケーション手法との違い
DESC法は交渉や合意形成に強みを持ちますが、ビジネスでは他にも有効なフレームワークがあります。ここではPREP法、SDS法、基盤となるアサーティブ・コミュニケーションと比較しながら、違いを整理します。
| 手法 | 流れ | 特徴 |
| PREP法 | 結論→理由→具体例→結論 | 要点を明確にし説得力を高める |
| SDS法 | 要点→詳細→要点 | シンプルで記憶に残りやすい |
| DESC法 | 事実→気持ち→提案→選択 | 双方向の対話で合意形成を目指す |
| アサーティブ・コミュニケーション | 特定の型はなし | 自分も相手も尊重する態度・姿勢 |
PREP法との違い
PREP法は「結論→理由→具体例→再度結論」という流れで話を構成する方法です。要点を冒頭と最後に置くため、説得力を高めたいプレゼンやスピーチに向いています。
一方、DESC法は相手とのやりとりを通じて合意を目指すため、交渉や相談に適しています。
SDS法との違い
SDS法は「要点→詳細→要点」と繰り返すことで、内容を理解・記憶しやすくする方法です。ニュースや短い説明に向いています。
ただし、相手の反応を踏まえた調整は含まれないため、双方向性を持つDESC法とは目的が異なります。
アサーティブ・コミュニケーションとの関係
アサーティブ・コミュニケーションは「自分も相手も尊重する姿勢」を意味します。
DESC法はその姿勢を具体的に実践する会話の型と位置づけられます。つまり、アサーティブが心構えだとすれば、DESCはその実行手段です。
関連記事: アサーティブコミュニケーションとは?意味や職場でのメリットやトレーニング方法も解説
まとめ
DESC法は、自分の意見を押し付けず、相手を尊重しながら建設的に話し合いを進めるために役立つフレームワークです。流れに沿って話すことで、感情的な衝突を避けつつ、双方が納得できる結論に近づけます。
この手法を活用すれば、信頼関係の構築、建設的な議論、誤解や衝突の回避といったメリットを得られます。ただし、相手が必ず納得するとは限らないことや、複数の選択肢を準備する必要があるといった注意点も理解しておくことが大切です。
ビジネスの場面ではもちろん、就職活動や日常生活でもDESC法は役立ちます。無理な依頼を断るとき、会議で意見を調整するとき、交渉や自己PRをするときなど、幅広いシーンで実践できるでしょう。
ポイントは「感情的にならず、事実と気持ちを整理して、相手と一緒に解決策を探す姿勢」を持つことです。最初は少しぎこちなくても、繰り返し意識して使うことで自然に身につきます。ぜひ今日から小さな場面で試してみてください。DESC法は、あなたのコミュニケーションをよりスムーズにし、人間関係を前向きに変えていく力になるはずです。