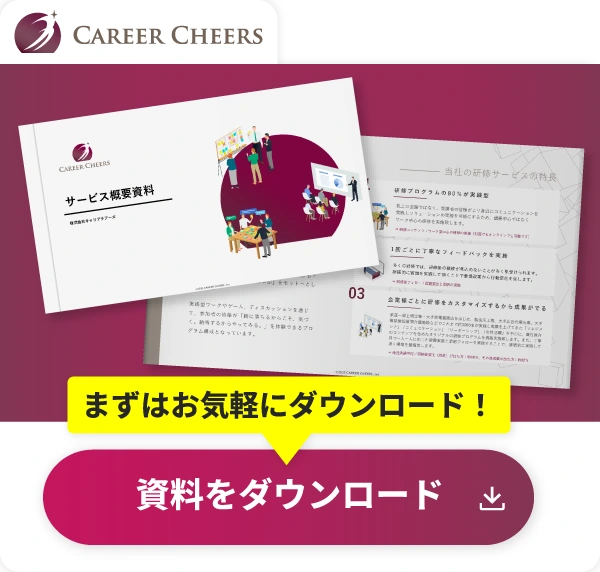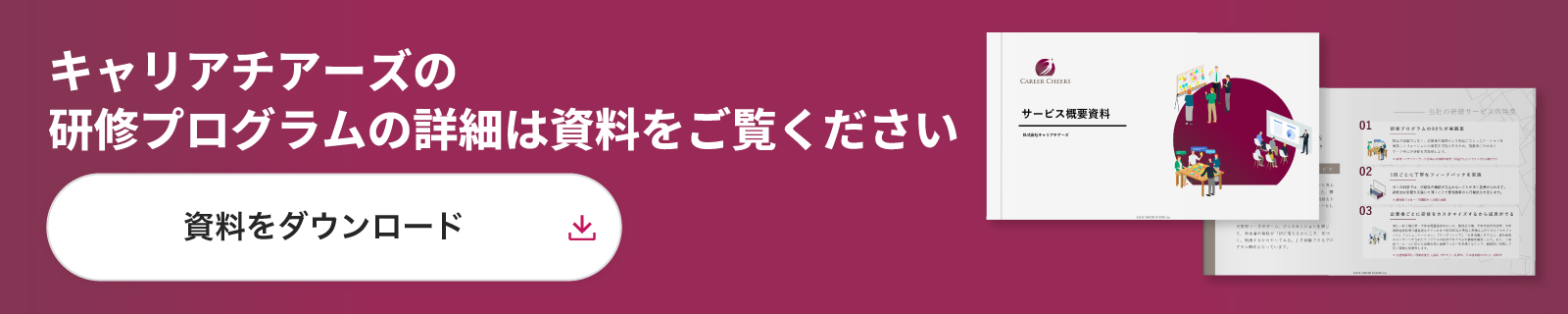
管理職になりたくない人が増えているのはなぜ?背景・理由から、企業の対策まで解説
「管理職になりたくない」と感じる人は年々増えています。かつては昇進こそが安定と成功の証とされていましたが、いまや若手を中心に「責任が重すぎる」「プライベートと両立できない」「待遇が見合わない」といった声が広がっているためです。
この記事では、管理職になりたくないと考える人が増えている背景や理由を解説します。また、企業がとるべき対策についても整理しました。
「なぜ管理職を避ける人が増えているのか知りたい」「部下から昇進を断られて悩んでいる」「自分自身が管理職に向いているのか不安」という方にとって、行動の指針となる役立つ情報をまとめています。
「管理職になりたくない」と考える人が増えている背景
近年は管理職への昇進を望まない人が明確に増えています。2025年度の調査では「現在の会社で管理職になりたい」が17パーセント台まで低下し、2021年から3年で大きく落ち込んでいます。20代では管理職希望が3割弱まで下がり、若手の志向変化が顕著です。(出典:パーソル総合研究所 働く10,000人の就業・成長定点調査 2025)
背景には働き方と価値観の変化、長時間労働への違和感、処遇への納得度低下が重なります。さらに役職のモデル不足も影響します。女性管理職比率は係長で23パーセント台、課長で13パーセント台、部長で1桁にとどまり、上位ほど少ない構造が続いています。(出典:男女共同参画白書 令和6年版)
管理職になりたくないと感じる主な原因と理由
まずは、管理職になりたくないと感じる主な理由と感じている不安を整理します。
| 理由 | 感じている不安 |
|---|---|
| 責任の重さ | チーム成果まで背負う負荷 |
| 人間関係 | 板挟みや育成負荷 |
| 労働時間の増加 | 休息や家庭時間が削られる懸念 |
| 処遇の納得感 | 手取り減少や評価不透明 |
| 専門性の喪失 | 現場スキルが鈍る不安 |
| 私生活との両立 | 育児や介護への不安 |
| 自己評価の低さ | 自信不足や未知への不安 |
| ロールモデル不足 | 将来像を描きにくい |
以下では、それぞれの理由と原因を詳しくみていきましょう。
責任の重さに対するプレッシャー
管理職はチーム全体の成果や職場の公正性を守る立場です。部下の判断も含めて最終的な責任を負うため、失敗のリスクを強く意識しやすいポジションといえます。背負う範囲が広がるほど基準が上がり、精神的な負担も増すのです。
現場で数字の未達やトラブル対応が続けば疲労は蓄積します。とくに若手は失敗を避けたい傾向が強く、「安定を選ぶ方が安全だ」と考える人も少なくありません。管理職の姿が「叱責と緊張」に結びついて見えるほど、挑戦意欲は下がってしまうでしょう。
部下の育成や人間関係が負担になること
管理職の大きな役割のひとつが「人を育てること」です。しかし、この育成や人間関係の調整に強いストレスを感じる人は多いものです。例えば、若手社員と定期的な面談、成果に対する納得感のある評価説明、メンタル面のフォロー、部署間の利害調整や顧客との折衝まで求められます。
「上からの要求」と「下からの期待」の間で板挟みになり、どちらにも気を配らなければならない状況は、心身の負担を大きくします。特に近年はリモート勤務が増えたことで、以前よりも人間関係の構築に工夫が必要になっている点も負担感を高めています。
労働時間の増加や残業への懸念
管理職になると「仕事量が一気に増える」というイメージが根強くあります。管理業務をこなしながらプレイヤーとしての役割も続けるプレイングマネージャーもおり、業務過多に陥りやすいのが現実です。
休日や夜間の対応が必要になる場面も多く、プライベートの時間を圧迫されるのではないかという懸念は常につきまといます。長時間労働に対する世代間の価値観の違いも影響しています。特に20〜30代は「働きすぎて生活を犠牲にするくらいなら昇進を断る」という考え方もあり、管理職を敬遠する流れを加速させています。
給与や待遇が役割に見合わないと感じる不満
管理職になっても責任だけが増えて収入は思ったほど増えない場合もあり、見合わないと感じる人もいるようです。
給与だけでなく評価が不透明で「成果が給与に反映されていない」と感じる社員も多く、モチベーション低下につながります。努力や時間の投資がきちんと報われないのであれば、昇進を望まないのは当然といえるでしょう。
自分の専門スキルを活かせない不安
現場で積み上げてきたスキルが活かせなくなるのではないかという不安も理由のひとつです。特に技術職や専門職志向の強い人にとって、管理業務に時間を奪われることは「自分の強みが失われる」ことにつながります。
役職に就くよりも専門スキルを深めたい、専門家として評価されたいと考える若手もおり、この志向の変化が管理職離れにつながっていると考えられます。
私生活や家庭との両立が難しくなること
育児や介護などのライフイベントを抱える世代にとって、管理職は両立を難しくする要因と見られがちです。
特に女性管理職の割合は上位役職になるほど大きく減少しており、「両立できるロールモデルがいない」という現実が不安を強めています。仕事と生活を両立できるイメージが描けないままでは、管理職を目指す決断は難しいでしょう。
自分は管理職に向いていないという自己評価
未経験ゆえの不安は大きく、適性がないと考えてしまいがちです。過去にリーダー経験が少ない人は、未知への負担を大きく感じてしまうでしょう。
自信の欠如は挑戦へのブレーキとなり、結果的に管理職志望者の減少を招いていると考えられます。
ロールモデルとなる上司が少ないことへの失望
最後に挙げられるのは「将来像が見えない」という理由です。社内に魅力的な管理職のロールモデルがいなければ、自分もその立場を目指そうという気持ちは生まれにくいものです。
特に、女性や若手の管理職が少ない職場では、「自分ごと」として昇進を考えにくくなります。結果として、管理職の候補者不足がますます深刻化する悪循環に陥ります。
企業や人事がとるべき対策
管理職になりたくない人が増えているのは、多くの会社にとって大きな課題です。ここからは、企業や人事部ができる主な工夫を紹介します。
主な対策は次の5つです。
- 報酬制度と評価基準の改善
- 管理職に必要なスキルを身につける研修制度の充実
- メンターや上司によるサポート体制の強化
- 働き方の柔軟性を高める制度設計
- 管理職像の再定義とキャリア支援
報酬制度と評価基準の改善
責任ばかり増えて、収入や手取りがあまり変わらない状況では、管理職を目指したいと思ってもらえません。役職手当を成果に合わせ、チームの成長や部下の育成も評価に含めることで「やりがい」と「収入」が結びつきます。
また、評価の指標がわかりにくいことも不満につながります。最初に基準をしっかり示し、途中でフィードバックを入れるなど、あいまいな評価ではなく数字や具体的な行動で判断されることで納得しやすくなるでしょう。
管理職に必要なスキルを身につける研修制度の充実
昇進前から段階的に学べる道筋を用意します。リーダーの必須基礎である目標設計、対話とフィードバック、評価の運用、業務設計、リスクと法令の基礎を体系化します。
着任時にはオンボーディングを設計し、現場の難題にすぐ向き合える状態をつくります。研修は一度で終えません。ロールプレイや現場課題の持ち帰りを通じ、学びと実務を往復させます。
メンターや上司によるサポート体制の強化
新任の管理職にとって「孤立感」は大きな壁です。そこで、経験豊富な先輩をメンターに指名し、月1回の1on1で相談できるなどの仕組みを整えると安心感が生まれます。役割の優先順位を一緒に整理できれば、業務の負担も和らぎます。
部門長が定期的にレビューし、過重負担が見えた段階で業務整理や権限移譲を支援するなど、管理職同士で事例や失敗を共有する勉強会を設ければ、悩みを抱え込まずに済みます。「支えてくれる仕組みがある」と感じられるだけで、昇進への心理的ハードルは下がっていきます。
働き方の柔軟性を高める制度設計
「時間の自由度がないから管理職になりたくない」と考える人も多くいます。
対策として、在宅勤務やフレックスを役職に関係なく使えるようにすれば、育児や介護を抱える人もキャリアを諦めない環境を整えられます。以下はその一例です。
- 会議は集中時間にまとめる
- 録画やチャットで意思表示できるようにする
- 制度を利用しても不利益が生じないよう文化をつくる
こうした工夫や柔軟性があれば、「管理職でも生活を犠牲にしなくていい」と思えるようになります。
管理職像の再定義とキャリア支援
「管理職=大変で報われない」というイメージを変えることも大切です。雑務や形骸化した承認などを見直し、意思決定や人材育成といった本来の役割に時間を割けるよう再設計する必要があります。
また、管理職だけがキャリアのゴールではありません。専門職として評価される道を並走させることで、それぞれの強みを発揮できる環境が整います。最近は専門職制度を導入する企業も増えており、キャリアの多様化は現実的な選択肢となっています。
加えて、社内の多様なロールモデルを積極的に紹介することも効果的です。具体例が見えるだけで「自分にもできる」と思える人が増え、志望者不足の解消につながるでしょう。
まとめ
管理職になりたくないという声が増えているのは、責任の重さや人間関係の負担、長時間労働への懸念、待遇への不満、生活との両立の難しさなど、多くの要因が絡み合っているからです。若手世代を中心にキャリア観が多様化するなかで、「管理職だけが成功の道ではない」という価値観が一般化していることも背景にあります。
しかし一方で、企業にとって次世代のリーダー不足は組織の成長を左右する深刻な課題です。だからこそ、報酬や評価制度の改善、スキルを学べる研修、メンターによるサポート、柔軟な働き方の導入など、環境を整えることが急務といえます。
企業と社員が互いに理解し合い、多様なキャリアの道を認め合うことで、組織にも個人にもプラスの未来が開けていきます。