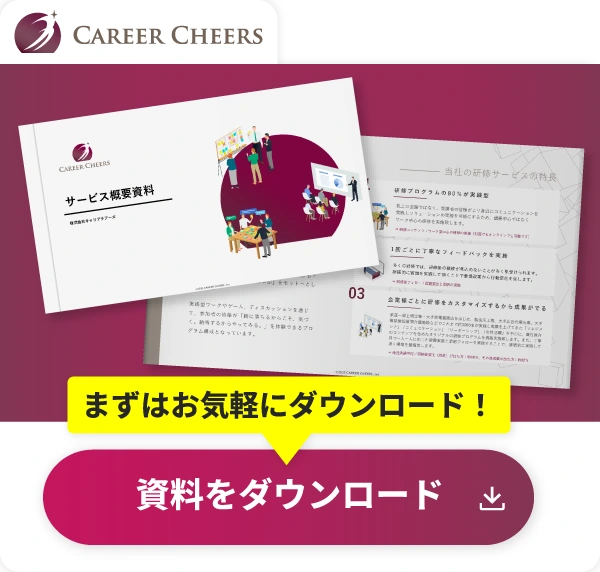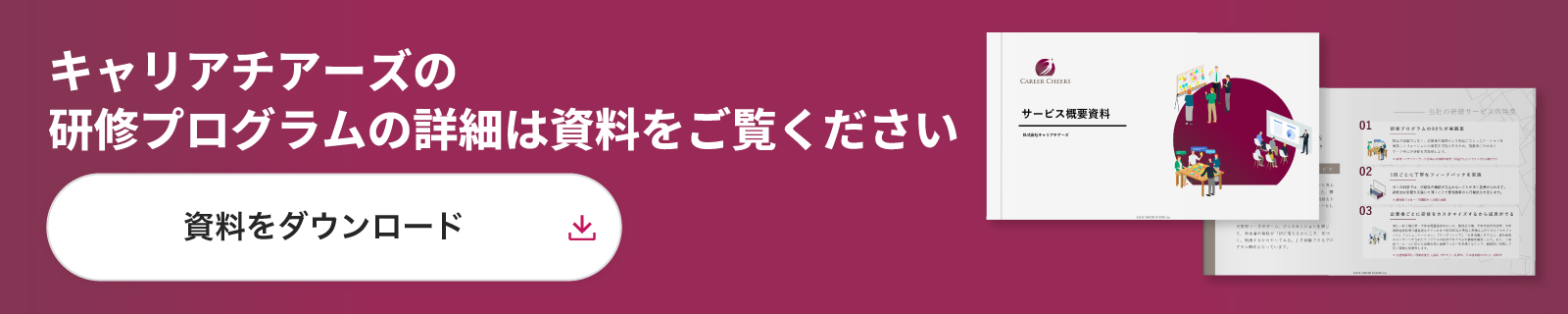
コンプライアンス違反とは?事例一覧と原因・防止策を徹底解説
コンプライアンス違反とは、法律だけでなく、社会的常識や社内ルールに反する行為全般を指します。違反が発覚すれば、企業の信用失墜や売上減少、時には倒産にまでつながる重大リスクです。
この記事では、労務・ハラスメント・情報漏えい・不正会計・品質不正・SNS炎上など、実際に起きた代表的な事例をわかりやすく紹介します。そのうえで、違反が発生する原因と、それを防ぐための具体的な対策を解説します。この記事を読むことで、自社が抱えるリスクを把握し今日から実践できる対策の参考としていただけます。
コンプライアンス違反とは
コンプライアンス違反とは、企業や組織が法律や社会的倫理、社内規程などのルールに反する行為を指します。具体的には、法令違反や社内規則違反、社会規範違反まで広範囲に及びます。
元々コンプライアンスは「法令遵守」の意味ですが、近年では法律だけでなく企業倫理や社会的ルールも含めた概念として捉えられています。こうした違反行為が起これば企業の信用は低下し、売上が落ち込むだけでなく、最悪の場合は経営破綻に至る可能性があります。
そのため、企業経営ではコンプライアンス意識を徹底し、違反の未然防止と早期発見に取り組むことが非常に重要です。
コンプライアンス違反は組織ぐるみの不祥事だけでなく、社員一人ひとりの行動にも及びます。些細に思える行為でも、資産の不正使用や情報管理違反として重大な問題に発展する可能性があります。だからこそ、全社員が自覚を持ち、一人でも違反を起こさないよう教育や管理を徹底することが求められます。
【事例一覧】代表的なコンプライアンス違反
ここでは、実際に発生し報道や公表が行われた代表的な事例を紹介します。
| 主なコンプライアンス違反の事例 |
|---|
|
多くの企業で起こり得るケースばかりです。自社に当てはめながらリスクを点検してください。
長時間労働・サービス残業
2015年、大手広告代理店・電通の新入社員が、月100時間を超える長時間労働の末にうつ病にり患しました。その後には同社員が度重なる過労によって自殺し、労災認定されたことで、同社は再発防止策を公表しました。
なお、安全配慮義務の判断枠組みは、最高裁判例(いわゆる「電通事件」)などで示されています。
(出典:最高裁判所)
パワーハラスメント
2014年、消防設備販売会社・暁産業の新入社員が、上司からの執拗な叱責や長時間労働により自殺。福井地裁はパワハラと自殺との因果関係を認め、約7,200万円の損害賠償を命じました。
(出典:労働判例 暁産業事件)
セクシャルハラスメント
2024年、大阪経済大学は、教授による教員への複数回のセクシュアルハラスメント行為を認定し、懲戒処分(諭旨免職)を公表しました。教育機関での事例ですが、組織内でのセクハラが職を失う重大処分に至る典型例です。
(出典:大阪経済大学)
個人情報の漏えい
2024年、NTT西日本の子会社で派遣社員が約928万件もの顧客情報を不正に持ち出し、第三者に故意に流出させていたことが発覚。公式に謝罪と再発防止策が発表されました。
(出典:NTT西日本)
2025年6月には、ソフトバンクが委託先で顧客情報約14万件が不適切に扱われた可能性を公表し、謝罪と調査を発表しました。
(出典:ソフトバンク株式会社)
架空売上・粉飾(不正会計)
2023年、日本旅行が全国旅行支援事業において勤務実態のない従業員分の人件費を不正請求。愛知県は最終的に約564万円の不正を確認しました。
(出典:愛知県)
帝国データバンクによると、2024年に倒産した企業のうち「粉飾決算」が95件で最多となり、コンプライアンス違反倒産は388件と過去最多を記録しました。
(出典:帝国データバンク コンプライアンス違反企業の倒産動向調査)
検査データの改ざん(製造・認証)
2024年6月、本田技研工業は国土交通省への報告で、型式指定申請において認証試験データに不適切な取り扱いがあったと公表しました。試験条件の逸脱や、試験成績書に実測値と異なるデータを記載するなどの不適切な事案があったことを確認したとされます。
(出典:本田技研工業)
表示偽装(小売・飲食)
2022年、築地魚市場が取り扱った冷凍メバチマグロで、中国産を「台湾産」と虚偽表示して販売していたことが発覚。農林水産省が指導し、消費者の信頼を大きく揺るがしました。
(出典:朝日新聞デジタル)
権限管理ミス(IT・Web)
2014年、ベネッセコーポレーションで委託先社員が約3504万件の顧客情報を不正に持ち出し、名簿業者に売却。権限管理の甘さが大規模漏えいにつながった典型例です。
(出典:ベネッセホールディングス)
記録改ざん(医療・介護)
2023年、厚生労働省は治験支援会社メディファーマにおけるデータ改ざんなどのGCP違反を公表しました。臨床試験の信頼性を揺るがす事例として大きく報道されました。
(出典:厚生労働省)
下請法違反(取引)
2025年5月、下請代金支払遅延等防止法の改正法が成立。公正取引委員会は運用方針・周知内容を公表しました。改正により、親事業者の手形払いの禁止や一方的な価格決定の抑止が強化されています。
(出典:公正取引委員会)
コンプライアンス違反の原因と防止策
コンプライアンス違反の背景には、以下のような共通の原因があります。
| 主な原因 |
|---|
|
これらを克服するには、組織全体で仕組みを整え、実効性のある運用を続けていくことが不可欠です。以下では、主な原因ごとに有効な防止策を整理します。
経営陣の姿勢不足とその改善策
多くの不祥事は、経営陣がコンプライアンスを軽視する姿勢から始まります。「結果がすべて」といった風土が根づけば、現場は不正や過剰なノルマに追い込まれやすくなります。トップは「不正はしない・させない」と明言し、自ら行動で示すことが出発点です。
そのうえで、通報への対応の早さや是正の進捗といった指標を経営会議でチェックし、役員報酬や管理職評価に反映させれば、組織全体での意識付けにつながります。
ルールや手順の未整備と整備のポイント
規程が古いまま放置されていたり、承認フローが属人的だったりすると、従業員は「何を守ればよいのか」を判断できません。労務・情報管理・取引・会計・品質といった重要領域ごとにポリシーを最新の法令や実態に合わせて整備し、責任範囲を明確にすることが必要です。
承認はシステム化して二重チェックを標準とし、定期改訂と理解度テストを組み合わせることで、形だけの規程になるのを防ぎます。
教育・研修の不足と継続的な学び方
「知らなかった」「昔は許された」という思い込みが違反の引き金になります。入社時や昇格時の研修に加え、eラーニングやケーススタディを取り入れ、継続的に学ぶ場を設けましょう。
特に管理職には、法改正やハラスメント防止、情報セキュリティなど最新の知識をアップデートさせることが欠かせません。短時間のマイクロラーニングや理解度テストを活用することで、知識の定着と実務への応用を促進できます。
部門同士の連携不足と情報共有の仕組み
縦割りの組織では、部署をまたぐ不正の兆候が見逃されがちです。営業部門の無理な納期が品質不正を招き、経理部門の違和感が現場に届かないなどの断絶をなくすには、法務・人事・経理・品質・ITを交えた横断的な会議を定例化することが有効です。
全社共通のリスク台帳を整備し、小さな異変でも経営層に共有される仕組みを持つことで、早期の対応が可能になります。
リスクの洗い出しと優先順位づけ
再発防止はリスクを正しく把握することから始まります。労務、情報、取引、品質などのカテゴリごとに想定される違反シナリオを洗い出し、発生可能性と影響度で評価しましょう。
頻度が高く影響も大きいリスクから優先的に対策を行い、軽微なものは中長期計画に組み込むのが合理的です。「洗い出し→優先順位づけ→実行→見直し」のループを定着させれば、限られた資源でも効果的にリスクを減らせます。
社内規程と承認フローの更新
特定したリスクに対しては、社内規程や業務プロセスを具体的に更新していく必要があります。例えば、ハラスメント防止規程や情報セキュリティポリシーを改訂し、契約書は法務レビュー後に決裁、勤怠は上限超過時に自動アラートが出る仕組みを導入するといった対応です。
経営層の恣意を避けるには、一定額以上の決裁は複数役員や社外取締役の承認を必須にすることも有効です。
監査・モニタリングの定着
仕組みを整えても、継続的に点検しなければ形骸化します。内部監査や抜き打ちチェックを定期的に行い、労働時間や経費、契約、ログ管理などを横断的に分析しましょう。
第三者監査を取り入れることで客観性も高まります。指摘事項は責任者と期限を定めて是正し、その進捗を役員会でレビューする仕組みを設けることが重要です。
通報制度と報復防止の仕組み
内部通報制度は、違反を最速で検知する仕組みです。社内窓口だけでなく外部弁護士や匿名フォームを設け、24時間受付可能にすると安心感が高まります。
通報者への不利益取扱い禁止を規程に明記し、違反した管理職は処分する方針を徹底すれば、通報が信頼される文化が根づきます。
eラーニングとケーススタディの継続
知識は時間とともに薄れていくため、単発研修だけでは不十分です。月次や四半期ごとの短時間eラーニングを配信し、理解度テストで定着度を測りましょう。
実際の不祥事やヒヤリハットを教材にしたロールプレイは、現場での判断力を鍛えます。教育と実務を繰り返すことで、従業員は自然に「違反を避ける選択」を身につけることができます。
関連記事:コンプライアンス研修が必要な理由を徹底解説!研修テーマや目的、効果的な進め方
まとめ
コンプライアンス違反は、特定の業界や一部の企業だけの問題ではなく、あらゆる組織で起こり得るリスクです。過重労働やハラスメント、情報漏えい、不正会計、品質データの改ざん、下請法違反、SNS炎上など、今回紹介した実在事例はいずれも企業の信頼や存続を揺るがしました。こうした事件の背景には、経営陣の姿勢不足、ルールや手順の未整備、教育の欠如、部門間の連携不足といった共通の要因があります。
しかし裏を返せば、これらは適切な仕組みと文化づくりによって未然に防止できる問題でもあります。リスクを正しく洗い出して優先度をつけ、社内規程や承認フローを最新化し、監査・モニタリングを定着させ、内部通報制度と教育を継続的に回していくことが重要です。
実際の事例から学び、自社の状況に照らして弱点を補強する取り組みを続ければ、コンプライアンス違反は減らすことができます。違反を防ぐことは、単なるリスク回避にとどまらず、社員の安心や顧客からの信頼を積み重ね、企業の持続的な成長につながっていくでしょう。