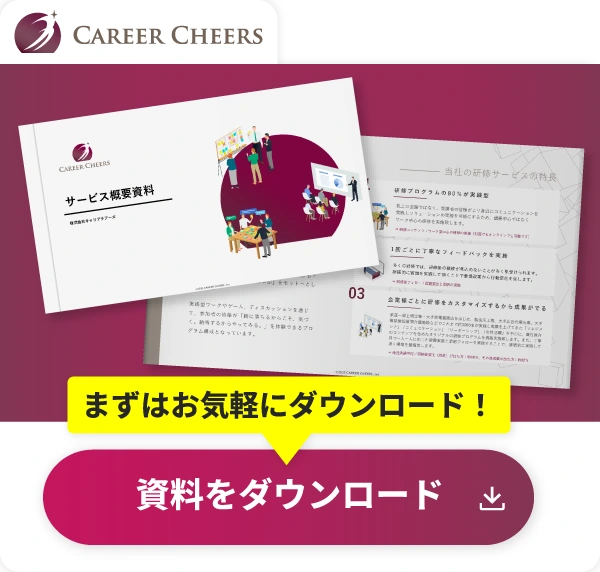アイコム株式会社 様
アイコムが挑んだ研修制度改革
ボトムアップによるさらなる風土醸成に意欲

少子高齢化による人材確保の難しさ、技術革新の加速、そして多角化する事業領域──企業が持続的に成長するためには、社員一人ひとりの力を最大限に引き出す仕組みが不可欠です。アイコム株式会社(以下、アイコム)は、創業以来60年以上にわたり、無線通信機器の開発・製造を手がけてきた企業です。この分野において長年の実績を持つ同社ですが、近年では事業の多角化が進み、ITや電波法、グローバルな通信規格など、より広範な知識が求められるようになってきました。製品の高度化に伴い、社員に求められるスキルも複雑化しているといいます。アイコムは、社員一人ひとりに学びの機会を提供するためにキャリアチアーズが提供する階層別研修制度を導入しました。
導入前の課題
属人的なマネジメントからの脱却と育成体制の再構築
アイコムでは長らく、体系化された研修制度が存在していませんでした。部長や課長クラスの多くの管理職は自身の上司の振る舞いを見て、仕事の学びを得るという、いわば“見よう見まね”の文化が根付いており、マネジメントスキルのばらつきが課題の一つとなっていました。過去には一部の幹部社員を対象とした外部研修への参加などもありましたが、対象者が限定されていたため、全社的な育成体制とはいえませんでした。特に若手社員や中堅層にとっては、成長の機会が限られていたのです。外部研修が実施されていた当時の社内の様子を、社長室の主任であり同社の研修プログラムの企画運営を担う山田氏は次のように述べました。
「外部研修というのは、経営層を志してもらうといった内容の研修だったのですが、やはり対象者が限定されており、階層別の研修といえるものではありませんでした。例えば、マネジメントについて知っている人と知らない人で二極化してしまっていましたし、マネジメントについての知識を持たない人たちは、自分なりに考えるしかない環境でした。」
さらに、少子高齢化の影響で人材確保が難しくなっている中、既存社員の能力を最大限に引き出すことが、企業の持続的成長にとって不可欠なテーマとなっていました。採用だけに頼るのではなく、「今いる人材をどう育てるか」が、経営の重要課題として浮上していたのです。
導入の経緯
社員の声が動かした、ボトムアップでの研修制度改革
研修制度導入のきっかけは、2024年に迎えた設立60周年を前に、2022年に行った取り組みでした。「百年企業」を目指すにあたり、課長・係長クラスの役職者を対象に「今後のアイコムに必要なことは何か」を問いかけるワークショップが実施されました。山田氏は研修サービスを導入する以前にあった社内の声について当時を次のように振り返ります。「当社は現在、『百年企業』という目標を掲げています。この目標に到達するために必要なものについて、キャリアチアーズの階層別研修を導入するよりも以前に、社内から意見を出し合うワークショップを設けました。そのワークショップで意見を出し合った際に、『人材育成のための研修が必要ではないか』という意見が圧倒的に多く集まりました。このワークショップ自体はトップダウンで始まったのですが、ボトムアップでも研修の機会を設けることが必要ではないかという意見を受けたことをきっかけに、研修サービスの導入を進めていきました。」
ワークショップ参加者の声を受け、社長室が主導する形で研修制度の導入が決定されました。人事部ではなく社長室が旗振り役となったのは、制度の意義を社内に浸透させるためであり、社員の業務時間を割いて研修を受けることへの理解を得るには、社内報や朝礼などを通じた継続的な情報発信が不可欠だったからです。
こうした危機感を感じていた矢先、キャリアチアーズからの提案を受け、提案内容が明確であったことから、前向きに研修サービスの利用を検討し始めたといいます。
「初回のご提案から正式な依頼まで1年以上期間が空いたのですが、その間、状況確認のお電話をまめにいただいたり、検討している研修を説明するとすぐに企画案を考えてくださったりと、ていねいにフォローアップしていただきました。ご提案の過程で弊社の課題に対して『研修ではこうしてはいかがですか』というお話を直接伺う機会もありました。キャリアチアーズ様は信頼できると感じました。」と山田氏は当時のキャリアチアーズへの所感を述べます。
そしてアイコムはキャリアチアーズとのファーストコンタクトから1年程度の期間を経て、研修パートナーとしてキャリアチアーズを選びました。
研修サービス導入当初は、社員全員に研修を受けさせるという方針ではありませんでした。初回の階層別研修は課長・係長職を中心に対象者約40名が受講し、研修受講後の感想をもとに今後の展開を検討するという慎重なスタートでした。
「キャリアチアーズの階層別研修を受けた受講者からは評判が良かったです。こうした研修参加者の意見をもって、研修実施の取り組みを継続することになりました。」(山田氏)
導入効果
社員の主体性と対話文化を育む研修制度の浸透と成果

社長室主導による研修制度の導入により、アイコム社内には「学んでもいい」「外部の知識を取り入れていい」という空気が醸成されました。これまで社内講師による研修が中心だった同社でしたが、外部講師を招いた専門的な研修も増加。無線機に関する電波法の研修など、部署ごとのニーズに応じた学びが加速しています。
社員からも「この研修を受けたい」「もっと学びたい」といった声が自然と上がるようになり、社会人大学への研究生派遣など、新たな育成施策も始まりました。
特に好評だったのがグループワーク形式の研修です。部長職向けの研修では、社長自らが参加し、動き回るほどの熱意を見せる場面もあったといいます。理論だけでなく、実践を通じてテーマの本質を理解することができると、多くの社員が手応えを感じています。
山田氏は同氏が入社した頃の会社の社風を現在と比較し、今の社風について言及しました。「私が入社した頃は平成でしたが、思い返せば、昭和っぽい昔ながらの会社の雰囲気があったと思うんです。ボトムアップで社員の声を吸い上げるといったことはあまり一般的ではなかったように思います。しかしながら、今はむしろボトムアップによる制度改革や意識改革が進んでいると感じます。こうした雰囲気が作られてきたことで、社員自身の会社に対する意見などが以前よりも耳に入ってくるようになりました。」
また、長らく制度として存在していなかった1on1(ワン・オン・ワン)面談も導入され、部下との関係性が大きく変化しました。上司が部下に「私に不満はありませんか?」と問いかけることで、双方向のコミュニケーションが生まれ、信頼関係の構築や部署の改善にもつながっていると同社の執行役員を務めるキャンプ氏は述べます。
今後の展望
研修を企業文化へと昇華
持続可能な人材育成体制の構築に意欲
社外との連携も進み、他社とのコラボレーションやM&Aなど、オープンな姿勢が強まっています。社員一人ひとりが外に向けてマインドを広げていくことが、これからのアイコムにとって重要なテーマとなるでしょう。
現在、研修制度は社長室が主導していますが、アイコムの研修制度についての展望を山田氏は次のように述べます。「今後は会社全体に正式な制度として研修を根付かせていくことが目標です。いずれはこの制度を長く定着させるためにもしかるべき部署のフローとして組み込んでいけたらと思っています。研修を通じて社員のマインドが変わり、それが社内文化を変えていく──そんな好循環を生み出すことが、今後のチャレンジです。」
管理職層には、世代間のギャップを埋めるためのコミュニケーション研修が必要であり、若手層にはロジカルシンキングの強化が求められているといいます。また、プレゼン資料の作成など、実務に直結するスキルの向上も研修を通じて習得していきたいと意欲を述べます。
「キャリアチアーズには、これまで200名以上のアイコムの社員を見ていただいており、今後も研修制度の定着と運営を支えていただきたいと考えています。」と山田氏はキャリアチアーズとの関係を、今後の意欲とともに語ります。
「企業の成長フェーズで壁にぶつかったときには、率直に話し合える関係でありたい──そんな関係を継続していくことができればと思います。」(キャンプ氏)